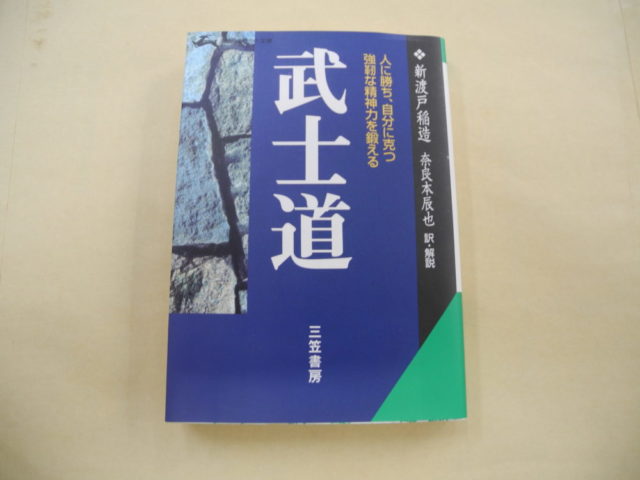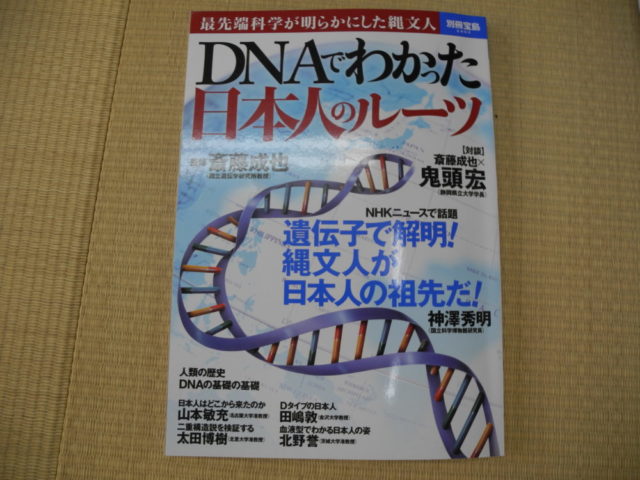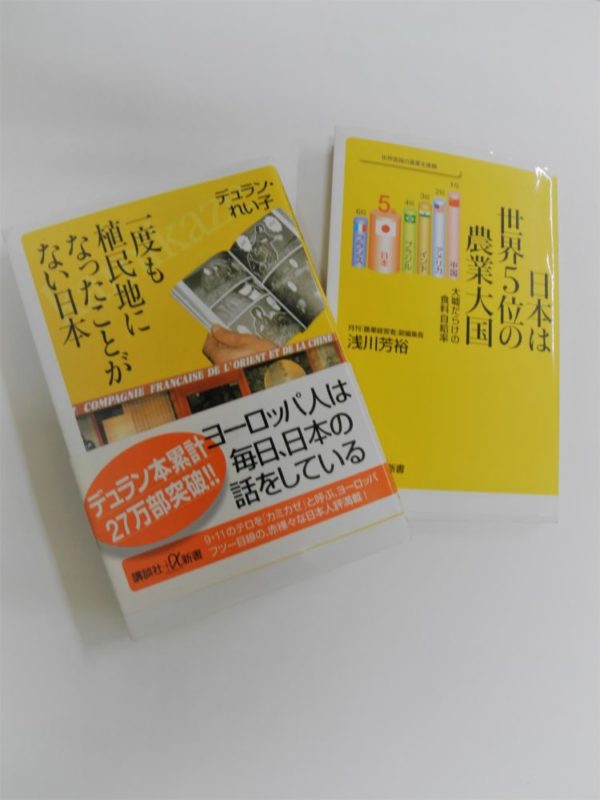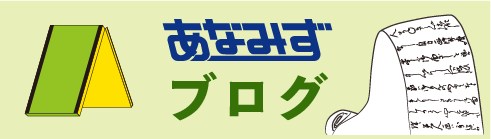2018-05-01
埼玉古墳群に行ってきました。
住所 埼玉県行田市佐間 駐車場 有(数か所)ます。
地域グルメは「行田焼きそば」・「フライ」・「ゼリーフライ」のお店が沢山あります。また、のぼり旗が多く見受けられます。
私達老夫婦は焼きぞばの小を注文しましたが食べきれず残しました。フライは私の子供のころのおやつと同じような味で懐かしく思いだました。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
埼玉古墳群(さきたまこふんぐん)は、埼玉県行田市にある、9基の大型古墳からなる古墳群。「埼玉古墳群 -古代東アジア古墳文化の終着点-」として世界遺産への登録を推進している。
県名発祥の地とされる「埼玉」の地にあり、前方後円墳8基と円墳1基の大型古墳が残る全国有数の大型古墳群である。現在は国の史跡として整備がなされている。
なお、かつては大型古墳の周りに陪臣の小型古墳があり、円墳35基、方墳1基からなっていた。しかし、昭和初期に周囲の沼地の干拓で取り壊されてしまっている。
- 各古墳の歴史については、主な古墳の各項リンク先を参照。
『日本書紀』によると534年、安閑天皇より笠原直使主(かさはらのあたいおみ)が武蔵国国造を任命され、埼玉郡笠原(現在の鴻巣市笠原)に拠点を持ったとされる。何の基盤もない当地に突如として、畿内に匹敵する中型前方後円墳が現れたこと、稲荷山古墳から出土した金錯銘鉄剣の銘に見える「ヲワケ」の父の名の「カサヒヨ」が「カサハラ」と読めることなどから考えれば、笠原を本拠とした武蔵国国造の墓ではないかという説[要出典]があるが、まだ不明確な点が多い。

丸墓山古墳下の石碑。指定地の村有化のための保存運動を記念して建てられた。(1940年建立)
古墳群は5世紀末から7世紀にかけて成立したと考えられている。
この地に古墳のあることは、江戸時代の『新編武蔵風土記稿』や『忍名所図会』(おしめいしょずえ)に記されている。また、付近に多くの古墳が存在したことは、「百塚」という字名からも知られる。 1893年(明治26年)には将軍山古墳が発掘された。1935年(昭和10年)の埼玉村古墳群調査で、前方後円墳11基、円墳11基が確認されている。1938年(昭和13年)8月8日には、9基の大型古墳が国の史跡に指定された。 1966年(昭和41年)以降、整備がはじめられ、1968年(昭和43年)に「風土記の丘」整備に先立つ航空写真測量で墳丘・濠の影(クロップマーク)が認められた[1]。同年8月に稲荷山古墳がその事業の一環として発掘調査された。この時出土した鉄剣から、1978年(昭和53年)9月の保存処理中に金象嵌銘文が検出されたことで、この古墳群が日本国中に知れ渡ることとなった。 その後、さきたま風土記の丘という公園として整備され(現在のさきたま古墳公園)、古墳のほかに移築民家(旧遠藤家、旧山崎家)、さきたま史跡の博物館、はにわの館(実際に埴輪を作ることができる)などがある。
埼玉県や行田市を中心として世界遺産への登録を目指しており、周辺の整備などを実施している。また、世界遺産登録の前段階として、国の史跡から特別史跡に昇格も視野にいれている[2] 。


主な古墳[編集]
鉄砲山古墳のすぐ東には浅間塚古墳があり、埼玉古墳群に含まれる場合がある。
埼玉古墳群の前方後円墳は、方形の多重周濠を持つことが明らかになっている。前方後円墳の周濠の多くは盾形をしており、方形の周濠は他に例が少なく[3]、埼玉古墳群の特徴の一つとなっている。また稲荷山古墳・二子山古墳・鉄砲山古墳・将軍山古墳の中堤に造り出しが付く点[4]、丸墓山古墳を除くと葺石が認められない点[5]、古墳の主軸がほぼ一定の方向を指している[6]などの特徴が認められる。
その他の古墳[編集]

円墳址(埼玉7号墳)大芝生広場として整備される以前は小円墳が8基あった。
風土記の丘として整備される以前は一帯が田畑であり、古墳はまったく整備されず野ざらしであった。そのため、小型のものの多くが明治末から昭和にかけて田畑や埋め立て用土として開拓された(さきたま古墳周辺は沼地が多く、農地には適していなかった)。
- 戸場口山古墳 - 方墳。1918年(大正7年)に消滅。現在は宅地で地中に周濠の痕跡が残る。
- 埼玉1号墳(天王山古墳(てんのうやまこふん)) – 円墳。
- 直径27メートル。築造年代は6世紀前半。頂上部に八坂社と神木杉があったが、1908年(明治41年)に合祀とともに伐採。古墳公園として整備される以前は宅地であった。
- 埼玉2号墳(梅塚古墳) – 円墳。麿塚古墳(まろづかこふん)とも。
- 直径24メートル。築造年代は6世紀前半。明治初期には大きな白梅があったが、1878年(明治11年)の冬に暴風によって倒れ枯失。
- 直径13メートル、高さ2メートル。築造年代は6世紀前半。水鳥埴輪出土地。
- 埼玉4号墳 – 円墳。直径18メートル。築造年代は6世紀前半。
- 埼玉5号墳 – 円墳。直径26メートル。築造年代は6世紀前半。
- 埼玉6号墳 – 円墳。直径22メートル。築造年代は6世紀前半。
- 埼玉7号墳 – 円墳。直径22メートル。築造年代は6世紀前半。
- 山宮古墳(さんぐうこふん) - 円墳。
- 将軍山古墳と二子山古墳の中間にあった。1906年(明治39年)に開拓。
- 直径40メートル。築造年代は6世紀の中頃。二子山古墳の西にあった。1981年(昭和56年)の排水路工事の際に発見。
- 高さ3メートル、全長45メートル。築造年代は6世紀後半。渡柳地区の西端にあった。1913年(大正2年)に開拓。1914年(大正3年)に埴輪数点が出土した。行田市No.95遺跡はこの古墳址とみられる。
- 渡柳地区の西側などに存在していた小円墳十数基(現在はいずれも開拓され消失)と、この大人塚古墳を含めて、「渡柳古墳群(わたりやなぎこふんぐん)」として区別することがある。
-
- この他、稲荷山古墳の東側などにも小円墳が存在していたことが伝聞や発掘により判明している。
-
-
-
円墳址(埼玉6号墳)
帰りに羽生の道の駅にメダカを買いにいきましたよ。メダカや金魚が手ごろな価格で販売しています。
楽しい一日を過ごしましたよ!
2018-04-20
『武士道』とは
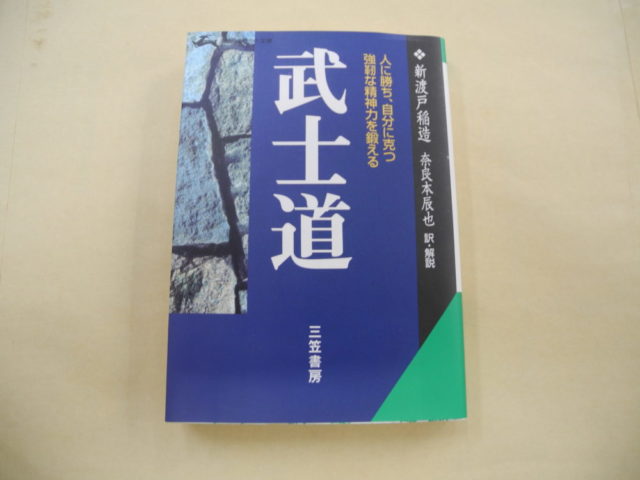
新渡戸稲造は、明治のあの時代、日本の伝統文化は西洋の道徳・宗教は遅れていないことを証明した人である。『武士道』の考えは封建的時代の武士社会の考えでもあるが、今日でも日本人の生活の中に道徳心として残っている。また、西洋の道徳はキリスト教と騎士道、その精神が残っており、やがて騎士道は無くなり、日本と違い紳士道として残っている。(ジェントルマン⇒紳士) 新渡戸稲造の『武士道』を読むと、世界に日本、日本人という国を知らしめたのである。時は明治、理解されない日本、日本人の心を世界中に日本人の本質を伝えたかったという思いが見えてきます。
新渡戸稲造は、アメリカ人の女性と結婚し、国際的にも日本人として多くの名誉を持ち、国際関連事業の仕事をして高く評価された。また、ユネスコ創立には第一人者として国際的にも認められている。稲造は生涯こんな言葉を残している。世界の国々には、他民族、他文明、他宗教があることを認めなければならないと言っている。また、人間は全て人間だから同じであるとも言っている。「人類は一つ」であるすべてを認めるべきであるとも言っている。話は戻ると現在『武士道』を右翼的考えともいわれるが、稲造の言うとしたことは、日本人は日本人らしく「自信の為、人の為、国の為」道徳心に生きることを世に伝えたかったのである。『武士道』の考え方を現在は少し間違った考え方、右翼思想と思っている人が多い。現在、日本社会は損得ばかり考え、日本人が持っていた道徳心を忘れています。一度『武士道』を読んで見ませんか。外国では、日本、日本人の考えが解らないときには参考書として世界中の全ての著名人は『武士道』を読んでいると言われています。
新渡戸稲造 『武士道』 奈良本達也翻訳より
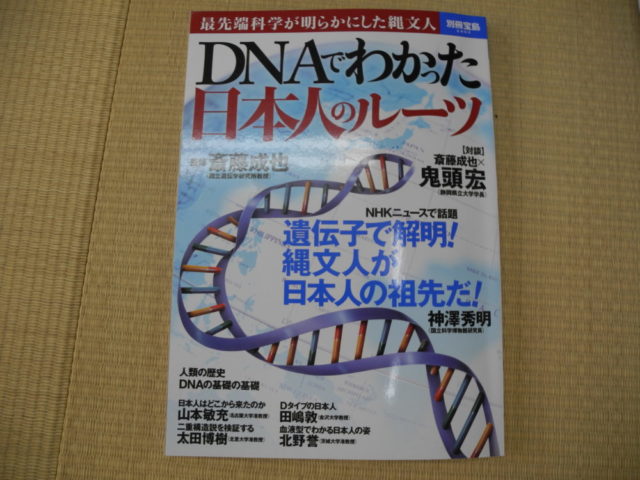
『武士道』とは「人に勝ち、自分に克つ、強靭な精神力を鍛える」こと
『義』とは義理、「正義の道理」
「正義の道理」私たちにとって、無条件に従うべき絶対命令であるべきではないのか
「義理」は本来義務いがいのことを意味していない。
『勇』「勇気」はこころの穏やかな「平静さ」によってあらわされる
まことに「勇気」のある人は、常に落ち着いて決して驚かされたりせず、何事によっても「心の平静さ」をかき乱されることはない。
『仁』はやさしく母のような「徳」である。「慈愛」は女性的な性質である「やさしさ」と「諭す力」を備えている。私たちは「公正さ」と「義」で物事を計らず、むやみに「慈愛」に心を奪われてしまうことのないように教えられている。
『礼』は「長い苦悩に耐え親切」で人を「むやみに羨まず」「自慢」せず思い上がらない。自己自身の「利」を求めず容易に人に動かされずおよそ悪事というものを「たくらまない」ものであるといえる。
「武士の心」とは 「志」
慈しみの心を持って常に相手を思いやり敬いながら、世界中の民族の共存共栄を計る。
i msorry (すいません)
thank you (ありがとう)
i ioveyou (愛しています)
この三つの言葉が、世界中の民族の共存共栄を計ると稲造は言っている。
新渡戸稲造 『武士道』 奈良本達也読書より
追記
最近、色々と社会を揺るがしている日本の政治家は日本という国をどのように考えているのかわかりません。特に○○〇党、野党などはとくに、また、官僚は国民の行政をどのように思っているか。日本国の為に、国民の為にとか道徳心はないのか。先人たちはこの国を良くしようと努力をしたのに、今の政治家、官僚には御身だけしか考えないと思うのは私だけですか。
大事にしょう。この国を!!
2018-04-13
人の心と我が家 -日本人の文化と伝統-

つい3年前の事件、もうお忘れた人も多いと思います。○○県のある女子高校生が同級生殺人を起こしました。この事件の悲劇をどのように思われますか? 当時の報道では、加害者は小学生の時から勉強が良くでき、また、スポーツの出来る子供と言われています。なぜ、同級生のお友達を殺害したのか?報道だと「人を殺してみたかった!」また、「人を解剖したかったから!」この少女は前もってホームセンターで刃物やノコギリを買っていての犯行と報道されています。なぜ、このような惨事になる前に家族やご両親は気が付かなかったか?報道の中から聞けば、近所でも評判の良い子だったようです。
私は思うのですが、この子は小さい時から布団に寝てそれも川の字に寝ていればこのような惨事を起こさなかったかもしれません。幼くして甘えること、泣くことなど、そこにはすぐに親兄弟が手を出してくれるはずだからです。もれも愛情いっぱいの生活を送れたはずです。両親や家族は自分を大事にしてくれることも理解するはずです。私は少年少女の事件がある時いつも思うのです。またこの家にも川の字で寝て居ないと思うのです。この事件の報道からは、お父さんは○田大学出身で弁護士、お母さんは東○大学教育学部出身で、ご夫婦とも教育熱心で、勉強さえできれば良いと言う考えの家庭ではないかと思うのです。
幼い時から家庭は裕福で物を与えられまた、やりたいことは全て与えられ、「我慢」と言うものは与えられなかったのではないか? 私の解釈ですが、小さいころから川の字で寝ると人は肌と肌が触れ合い また、心と心が繋がり人に対しての愛情が出るのです。これも大人になっても人様を大事にすることは同じです。動物も見てください。子育ては常に集団への生き方を教え、また、親と肌と肌が常に触れています。

日本の伝統や文化は西洋の文化とは違うはずです。西洋のイスやテーブル・ベットが入ってきたのは幕末になってからです。近年大半はイスやテーブル・ベット生活する人が多くなり、人と人の繋がりが希薄になり、社会は急速に歪み始めています。イスやテーブル・ベットは、人と人の距離を離す。ただ儀礼的では良いのですが、また、利便性からでも日本人は心と心は繋ぐことはできません。偉そうなことを言えば、教育とは、「ただ知識や技術を教えることではなく、「生きる力」や「我慢」を身に付ける」こと
畳の上で、強く子供を抱きしめてください。きっと良い子に育ちますよ
大事にしましょう。畳生活と川の字、日本の伝統・文化を・・ 穴水美樹
八王子FM 2018年4月~6月号 投稿より 『八王子FM77.5mh検索 パソコンからも聞こえます』
2018-04-07
「組織力」渡部昇一先生の話しから

組織力の名言でイギリスのネルソン総督の『見的必殺』見(けん)敵(てき)必殺(ひっさつ)は話が有名である。「相手が見えたら命を懸けて相手がいなくなるまで戦え」と言う話です。これがネルソン精神、現在でも起業者の志はこのネルソン精神が生き続いています。組織は目的単純が目的で、これが成功の道と言われていまいす。やはりそれには理想主義が根底にあり成功への道ともいわれています。企業は単純明快利益を上げれば良いのです。企業理念 例えば松下幸之助さんの話は水道からコンコンと流れる水は沢山あるから誰が飲んでも盗んでも誰も文句を言わない。自分も水道のようにたくさん作ってやれば皆に行きわたるし安く買うことが出来、また、喜んでもらえると言う発想だったそうです。これが水道哲学として有名な話です。トップは先ず、哲学・理念・使命感 ただ利益だけ追求では周りの人たちが付いてこなくなる。また、参考書だけ見ていると何も生まれないことを忘れてはいけない。自分の信念・哲学が大事である。

松下さんの話の中に多くの人と知り合って、アイデアや特許を取ったときは儲かっているが、次の商品開発を疎かにし、大抵倒産してしまう人が多い。松下さんは次の開発努力を惜しまなかったという事です。ようは色々な解釈はどうでもいい、単純明快にここぞと決めたらまっしぐらに進むこと。トップは常に同じ手や事をならない。トップは明るい人であること、大きなビジョン・目的目標が必要である。また、一つ一つの局面にたいして戦術が必要とされる『見的必殺』見(けん)敵(てき)必殺(ひっさつ)単純明快が必要とされる。周りは動きやすくすること疑惑が起こらないようにする。困難がおきたら次から次へと知恵を出して、また、周りの人を明るくすることが出来るのがリ-ダ-・トップの考えです。
※ ネルソン総督(イギリス最大の英雄とされる) 1758-1805 アメリカ独立戦争・ナポレオン戦争・活躍。
私の好きな著名人
渡部昇一先生は、上智大学元教授 (英文学・歴史論・社会論・政治論・古書の収集家など) 保守論客者
昭和5年山形県鶴岡市生まれ平成29年4月17日86歳没
上智大学文学部英文科・修士課程修了 ドイツ留学・イギリス留学
エピソ-ド
1 蔵書2位 貯蔵書籍15万冊 (現存する著名人で蔵書 立花隆さん10万冊 3位) 2017年度
2 大学時代の成績は常に一番ではなく100点を目指していた (理由は奨学金が欲しくて、100点の上は居ないからという理由と人と争うことが嫌なために、全ての科目を、親からの仕送りが絶えたてきたから、時代は戦後貧しい時代であった)
3 出版書籍600冊位と言われております。一番有名な本「知的生活の方法」ベストセラ-
2018-04-03
飛鳥山公園(東京都北区)に行ってきました。

当日は「春うらら」多くの人がお花見をしていました。飛鳥山は八代将軍徳川吉宗が桜の名所と仕立上げたところです。江戸っ子たちの行楽の場所で、落語にも飛鳥山が登場します。当時も今も桜の名所は、上野、芝、浅草、深川でもあります。飛鳥山は後に渋沢栄一の別荘として使われ、明治という時代を作り上げたのもこの場所からかもしれません。花見をさて置き、私は3館の資料館に探訪してきました。飛鳥山公園内には、現在は渋沢栄一史料館や紙の博物館、北区飛鳥山博物館として至っております。





一度は行っては如何ですか!
現在を知る意味で渋沢栄一氏の人生は楽しいです~よ~
2018-03-22
こんな気になる記事がありましたので、お読みませんか ?
「止めることなく命は繋がっている!!」
「つながってゆくこと」 文・河瀬直美 かわせなおみ/映画監督
全国信用金庫協会「たのしい我が家」ずいそうより
丁寧な暮らしを心が掛けている。たとえばどんなに忙しくても玄関と床の間のお花はいつも元気である事。神様の榊と仏壇の仏花の水はきちんと毎日変える事。お庭には季節の花が咲いている事。これらはいつ頃からかわたしの日課となった。学生時代は家のことなどちっともしなかったのに、高齢の養母が健在だった頃にそのようなことをできていればもう少しは彼女の心も穏やかだったろうか。けれど、何も教わることなくあの頃を過ごしたというのに、彼女の気配がわたしに宿り、気がつけば彼女のやっていたことを自らおこなっていたことに驚く。血のつながりはなくとも、共に生活をする、その日常の中で「家族」であることの絆は深まってゆく。

生まれた時には両親が別居をし、ほどなくして離婚をしたという。母と暮らした記憶はなく、父の存在は二十歳を過ぎて初めて知る事となった。母方の祖父の姉夫婦が子供に恵まれなかったことから、生まれた私を引き取って育てた。若すぎる二十四歳の母には新しい人生が待っていたのだ。やがて母が再婚をした相手を中学生になるまで本当の父親だと思っていたが、違った。そんな事情が重なり、生まれた時の苗子からすると、今の「河瀬」はわたしにとって四つ目の名となる。使え古してつかえなくなったものを捨てる時「お世話になりました」と声かけてゴミ箱に捨てる事。旅先での宿を去る時におじぎをして「おおきに」とその空間に感謝する事。朝陽に手を合わせ、月に話しかけ、道ばたのお地蔵様に「まんまんちゃんあん」と頭をさげる事。彼女の生活を通した所作は知らず知らずのうちに私の信じるものとなってゆく。特定の宗教によるでもなく、自らの周りにあるものと共に生き、感謝の心を持つ。ただそれだけのことが、自らをよき方向に導きはじめる。誰も見ていないからといって物事を粗末に扱うことのないように、知らず知らずのすちに犯している罪を見つめる勇気をもつように、人と人の狭間にあって君は能力を発揮するだろう、と高校時代の恩師は卒業のメッセージボードに書いてくれた。

そのことの意味をあれから三十年経った今、想う。若い時代にさまよった道は、ようやくその先が明るさと共に開けてみえるようになった気がする。わからないからこそその無謀なエネルギー若さゆえの情熱と相まってその時にしか創れないものを誕生させた。史上最少年でカンヌ映画祭の新人監督賞に輝いたことに恥じない作品づくりとは何だろう。きっといつもになっても、ハングリ-である事。明るく見え始めた道に安心せずに、その道が平坦でないことを確かめながら、一歩一歩自分の足で歩いてゆく事。表現するという事は、自らの日常にも責任をもって在るという事だと今思う。明日も続く日々に感謝し、表現を続けてゆく事。「河瀬」の名でこの時代に遺す作品を創る事。それが人々の未来に光を与えられることをねがっている。
河瀬直美 かわせなおみ/映画監督
「もがりのもり」第60回カンヌ国際映画祭 審査員特別大賞グランプリを受賞する
全信用金庫「たのしい我が家」ずいそうより
2018-03-21
今日は、春文の日、朝から雪が降っている。お墓詣りも行けず「そうだ今日は本屋に行こう」
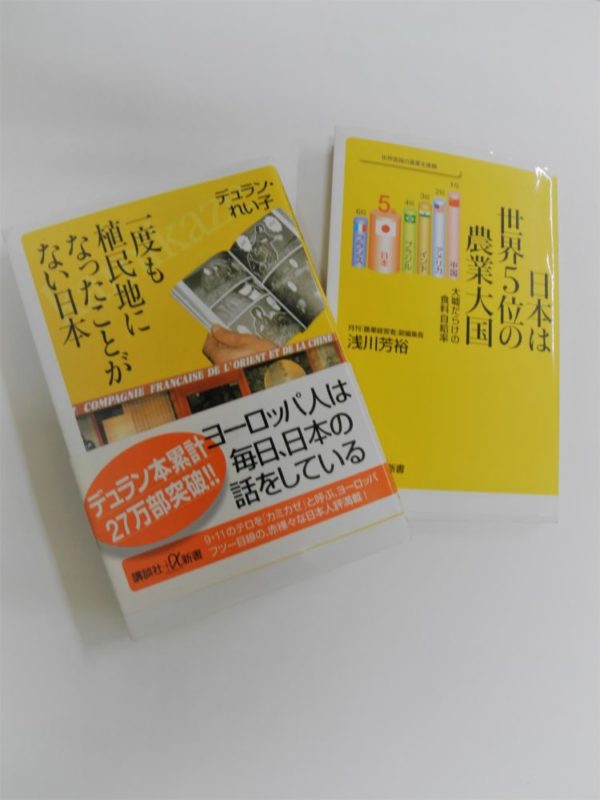
この2冊を朝から読みました。日本人の「すばらしさ・誇り」を新たに認識しました。
2018-03-17
こんな生き方は・・・いかがですか?
先ずは、あなたにとって誰が大事で、誰が大事ではないか!!
この話は、今から40数年前にある職人さんの親方から聞いた話です。

私が結婚する前の話しです。「穴水君、結婚してからの生き方を教えてやるよ。日本人には、生き易い生き方の順序があるんだよ」と言われました。それも楽しく生きるためにね。「それはね、結婚して1番大事な人は誰と思う」私は両親と答えました。「いやいや、それが違うんだ。先ず1番大事な人は結婚相手、パ-トナー(奥さん)だよ 2 子供 3 近所 4 パ-トナーの両親 (相手) 5 自分の両親 6 パ-トナーの兄弟 (相手) 7 自分兄弟 8 友達 9 職場の人
このような生き方を教えて頂きました。「要は、奥さんは他人なんだ。だから他人をよくすること、日本人がやることなんだ。それだから奥さんを大事にして、子供を大事に育て上げる。次は近所だよ。近所と仲良くすることで困ったときに助けてもらえる。昔から、遠くの親戚より近くの他人と言う言葉があるでしょう。それに自分の両親ではなく相手の両親や兄弟を大事にすれば、あなたの奧さんも貴方の両親や兄弟を大事にしてくれると思うよ。夫婦は思いやり、助け合いだよ。子供は育成すること、育て上げることだよ。そのような考えを持っていけば、あなたの周り人も貴方自身も生きやすく生きられるよ」と教えられました。
私自身こんな生き方があるとは思いもよらず考えさせられました。どうでしょう・・・いかがですか?
この生き方は日本人しか解らない生き方と思います。

また、子育てについても教えて頂きました。「子供は親の言うことを聞くのは3歳か4歳ぐらいまで」また、「子供にも人格があることを忘れてはダメ」と言われました。「10歳過ぎたら大人と同じように人格を作ってやること、親がバカであれば子供もバカと思った方がいいんだ。子供に教育を付けようとするなら、親がテレビを見ないこと、子供が勉強する時にバカな親はテレビを見て笑っている情けない親、子供が勉強する時は、親はテレビを消し、何でもよいので興味ある雑誌を読み、趣味の時間を作ること。子供も親も共通な時間を作ること。そうすれば少しは賢い子供になる」と言いました。私もなるほど思いました。

このような生き方をすれば、家族や親せきなど全てにおいてみんな、必ず幸せになり社会が明るくなると思います。今からでも遅くない、こんな生き方をしませんか ?
ちっと畳の上で考えませんか!!

※余談 子供と認める年齢は10歳迄とする。
(10歳過ぎたら子供に人格を作ってやることが大事です。また、一人の人間として社会に適用できる人間になると思います。10歳過ぎたら大人と同じです。ちっと自分自身の事を考えてみてください)
2018-03-07
今日は、江戸しぐさと言う話しです。
ちっと、生活を見直ししませんか ?
『 江 戸 し ぐ さ 』と言う言葉 ・・・知っていますか?
「江戸しぐさ」 というのは、江戸商人の代表各の人達の考え方、口の聞き方、表情から身のこなし方などについて、美意識や感性の全てを考え、商人の生活哲学を作ったと言われています。このことは現在にも通用することと考えられます。
江戸しぐさ であるとされる例

江戸しぐさ であるとされる例
1 傘かしげ
雨の日に互いの傘を外側に傾け、ぬれないようにすれ違うこと
2 肩引き
道を歩いて、人とすれ違うとき左肩を路肩に寄せて歩くこと
3 時泥棒
断りなく相手を訪問し、または、約束の時間に遅れるなどで相手の時間を奪うのは重い罪(十両の罪)にあたる。
4 うかつあやまり
たとえば相手に自分の足がふまれたときに、「すいません、こちらがうかつでした」と自分で謝ることで、その場の雰囲気をよく保つこと

5 七三の道
道の、真ん中を歩くのではなく、自分が歩くのは道3割にして、残りの7割は緊急時などに備え他の人のためにあけておくこと
6 こぶし腰浮かせ
乗合船などで後から来た人のためにこぶし一つ分腰を浮かべて席を作ること
7 逆らいしぐさ
「しかし」「でも」と文句を並べ立てて逆らうことをしない。年長者からの配慮ある言葉に従うことが、人間の成長にもつながる。また、年長者への啓発的側面も感じられる。
8 喫煙しぐさ
野暮な「喫煙禁止」などと張り紙がなくてとも、非喫煙者が同席する場では禁煙をしない

余談
日本人は、人に迷惑をかけないと言う社会は昔から出来上がっていたと言うことです。良い伝統はいつまでもつづいて欲しいですね。
ちょと、畳の上で ゴロ ゴロ して考えてみませんか?
畳の良さがわかるはずです。
ちっと、生活を見直ししませんか ?
気が付いたら直ぐに自分自身を、『 直しましょう.替えましょう 』
これぞ、日本人の習慣
2018-03-06
「情報」 情報ってなんですか?
最近、良い情報か、悪い情報か解らないのですが マスコミが垂れ流す情報は何かって言えば安部総理一色 ? 他は株価の値下がり情報です。株取引をやらない人には関係のない話と思うのですが、況して私には関係がないことです。いやいや、ふっと考えてみました。国会議員のみなさ~ん、もっと国民にとって大事なことがあるはずです~ょ~

ヘリナシ畳・龍球表 ( ↑ 昔からの本物畳)
マスコミの皆さんに畳生活のいい情報がありますよ~ お願いし~ま~す。
タタミのいいはなし!!
1 「安全・安心」 畳の上の生活は転んでも怪我をしにくい。
理由は住宅の中で一番柔らかい床材です。
2 「環境・自然」 畳の表はい草が良い香りを出す。
理由は天然素材です。(工業製品では味あえない)
3 「絆・癒し」 畳の上での座卓や布団での生活は家族の絆が深くなる。
理由は前文の通り
こんな情報をマスコミの皆さんが毎日毎日流していただければ、畳離れを食い止めることができると思うのですが ~
マスコミの皆さん~ 畳は絶対にいいんですよ~ 畳の上の生活は幸せになりますよ~と・・・
どなたか、こんな情報を流してもらえますか~?

こんな、いやなはなし!!
最近こんな話が多いのです。ご年配者はもう「死にたいね~」とよく言います。なぜなんでしょう。
よく聞くと、子供に迷惑をかけるから早く死にたいんですよ~
況して、パートナー(連れ合い)が無くなれば余計に「死にたいね~」と言います。
私は必ず言います。「子供を育てたダチンを返してもらえばいいじゃないですか」昔の世の中はオダチンと言ってご褒美をいただいたものです。ダチンは良い事をしなければくれなかったはずです。子供を育てたダチンを老いてからの子供に返して貰えると思えばいいんじゃないですか~
子供には、絶対に言ってイケないこと「俺は、私は、貴方(子供たち)たちに絶対に迷惑をかけないからね!」この言葉は死んでも言ってわいけない言葉です。本来、命、家族は永遠続くものです。自信の自命はたかが100年と思っても、親から子供へ、子供から孫へ命は受け継がれていきます。これこそ「栄枯盛衰・えいこせいすい」です。「必ず誰しもが老いる子供、孫みな同じ、また、同じ人生を辿るのが人間であると思う。 老いては人に迷惑をかけるのは当たり前と思ったほうがいいんじゃないですか」と言っています。
人から人へ 家族から家族へ、人のつながり、家族のつながり「栄枯盛衰」です。
ふと、思うんです。子供との関係はどうなっているのかな~と思います。こんなことばっかり言って・・・・・
親が悪いのかな~・・・子供が悪いのかな~・・・
こんな淋しい親にして・・・・子供はいいのか~な~
遠くにいる子供さんは畳が好きなのかな ~
平成30年3月5日 記
« Older Entries
Newer Entries »